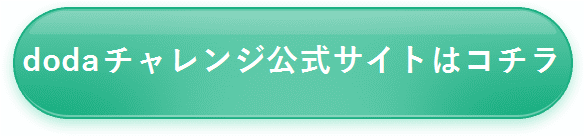dodaチャレンジで断られた!?理由や断られる人の特徴を徹底解説


dodaチャレンジで断られることがあるって本当?どうしてそんなことが起きるの?
dodaチャレンジにせっかく登録したのに、「ご紹介できる求人がありません」と断られてしまった経験がある方もいるかもしれません。思い切って転職活動を始めたのに、出鼻をくじかれるようでがっかりしますよね。でも、実はこれにはきちんとした理由があるんです。
dodaチャレンジから断られてしまう背景には、企業とのマッチングの観点や求職者の条件が影響していることが多いです。ですが、その理由を知っておくことで、次のアクションに繋げやすくなりますし、転職成功への近道にもなります。
この記事では、dodaチャレンジで断られる原因とその対策を、わかりやすく解説していきます。もしも「なぜ自分が断られたのか分からない」とモヤモヤしている方がいれば、この記事を読むことでスッキリ解決できるはずです。

dodaチャレンジで断られる理由には明確な傾向があるんだね。原因を知って対策を立てれば、チャンスはきっと広がる!
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、求職者が希望する条件と企業側が提示する求人内容がうまく噛み合わないと、紹介できる仕事がないと判断されてしまうことがあります。特に条件が厳しい場合には、その傾向が顕著になります。
- 希望条件が厳しすぎる
- 希望職種や業種が限定的
- 勤務地が狭すぎる
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
在宅勤務しかダメ、完全フルフレックスがいい、最低でも年収500万円以上ほしい――このような条件が高すぎると、該当する求人は一気に減ってしまいます。特に障がい者雇用では企業側に一定の配慮が求められるため、柔軟性がない条件は紹介の妨げになります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
アートディレクターやイラストレーターなど、特定分野に強いこだわりがあると、それにマッチする障がい者求人はごくわずか。障がい者枠では事務職や軽作業などが多いため、希望が限定されすぎると紹介されにくくなります。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方では、そもそも求人の数が少ないことが多いため、エリアを限定しすぎると紹介自体が困難になります。通勤範囲を広げたり、在宅勤務の選択肢も視野に入れることで、可能性を広げられます。

条件を少し緩めるだけで、紹介される求人がぐっと増える可能性があるんだね!
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジでは、一定の基準を満たす求職者をサポート対象としています。そのため、状況によっては登録してもサポートの対象外と判断されることがあります。
- 障がい者手帳を持っていない
- ブランクが長く、職務経験が少ない
- 体調が安定しておらず、就労が難しい
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジは障がい者雇用を前提としたサービスであるため、障がい者手帳を所持していない場合は、基本的に求人紹介を受けることができません。手帳の取得見込みがある方は、役所などで手続きを検討するのも選択肢の一つです。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
働いた経験が少なかったり、ブランクが数年あると、企業からの採用ハードルが高くなる傾向があります。いきなりフルタイム勤務を目指すのではなく、まずは短時間の仕事から始めたり、スキルアップを目指す訓練を受けることもおすすめです。
体調が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
面談などで、働くことに対する不安や体調の波が大きいと判断された場合は、就労移行支援の利用を勧められることがあります。就労移行支援を通して生活リズムを整えることが、安定した仕事に就く第一歩になるでしょう。

自分がサポート対象外かも?と思っても、就労移行支援など他の方法もあるから、前向きに次のステップを考えられるね!
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジの面談では、希望条件や適性について詳しくヒアリングされます。その際、準備不足や説明の不十分さが目立つと、「紹介が難しい」と判断されることがあります。
- 障がい内容や必要な配慮がうまく伝えられない
- 仕事へのビジョンが不明確
- 職務経歴をうまく説明できない
障がい内容や配慮事項が説明できない
自分の障がい特性や必要な配慮事項を明確に伝えることは、求人を紹介してもらううえでとても重要です。具体的にどのような職場環境なら安心して働けるのか、事前に整理しておくとスムーズに話が進みます。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「何でもいい」「とにかく仕事がしたい」という曖昧なスタンスでは、dodaチャレンジ側も紹介先を絞り込めません。ある程度でも希望の業種や職種を伝えると、紹介の精度がグッと上がります。
職務経歴がうまく伝わらない
これまでの職務経験を正確かつ簡潔に伝えることは、面談時にとても大切です。事前に職務経歴を整理しておくことで、自信を持って説明できるようになります。

面談に備えてしっかり準備しておけば、自分に合う求人とマッチしやすくなるね!
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
住んでいる場所や働き方の希望によっては、該当する求人が非常に少なくなり、紹介が難しくなるケースもあります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
地方では都市部に比べて求人数が少なく、勤務地の柔軟性が求められます。場合によっては通勤エリアを広げたり、交通手段を見直すことも選択肢になります。
完全在宅勤務のみを希望している場合
dodaチャレンジは全国対応ですが、完全在宅勤務に絞ると求人が極端に限られることがあります。通勤可能な範囲での勤務も視野に入れると、紹介の幅が広がります。

条件を少し見直すだけで、思いがけない良い求人と出会えるかもしれないね!
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジでは、登録情報の正確さが非常に重視されます。意図せず記入ミスや不正確な情報を入力してしまうと、サポートが受けられないことがあります。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
手帳をまだ取得していない状態で「取得済み」と登録すると、企業とのやり取りでトラブルになる可能性があります。事実と異なる情報は絶対に避けましょう。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
まだ就労できる体調や状況でないのに登録すると、マッチングが難航します。無理をせず、まずは回復や準備を優先しましょう。
職歴や経歴に偽りがある場合
虚偽の記載は、面談や企業との面接時に大きな問題となります。信頼を得るためにも、正確な情報を記載しましょう。

正しい情報を登録することが、信頼ある転職サポートの第一歩になるね!
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジから求人紹介を受けても、実際には企業の選考で不採用となることもあります。それが「dodaチャレンジに断られた」と感じる原因になることもあります。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業ごとに採用条件や社風が異なるため、マッチしないこともあります。ひとつの結果に一喜一憂せず、複数の選択肢を持って進めることが大切です。

一社に断られたからといって終わりじゃない!いろんな求人に挑戦しよう!
dodaチャレンジで断られた人の体験談|なぜ断られたのか?口コミから見えたリアルな声

実際にdodaチャレンジで断られた人って、どんな理由だったんだろう?リアルな声が知りたい!
dodaチャレンジを利用しようとして断られてしまった人たちの声を集めてみました。希望条件や経歴、体調の状況など、さまざまな理由で求人紹介が受けられなかったという体験談が寄せられています。ここでは、その一部をご紹介します。
体験談1・軽作業の派遣経験のみで、資格やスキルがなかった
障がい者手帳を持っていましたが、職歴は軽作業の派遣のみ。PCスキルもタイピング程度で資格も持っておらず、「紹介できる求人がありません」と言われてしまいました。
体験談2・継続的な就労が難しいと判断され、就労移行支援を提案された
面談で「継続就労できる状態ではない」と判断され、まずは就労移行支援を利用しましょうと案内されてしまいました。
体験談3・長期ブランクがあり、まずは体調安定を優先するよう言われた
精神疾患で長期間療養しており、ブランクが10年以上ありました。dodaチャレンジからは「まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう」とアドバイスされました。
体験談4・地方在住+専門職希望で、求人がなかった
四国の田舎町で在宅のライターやデザイン職を希望したところ、「ご希望に沿う求人はご紹介できません」と言われました。
体験談5・正社員経験がなく、紹介が難しいとされた
これまでの経歴はすべてアルバイトや短期派遣。正社員経験がないため、「現時点では正社員求人の紹介は難しいです」と言われてしまいました。
体験談6・条件が厳しく、すべてを満たす求人がなかった
完全在宅、週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を提示したところ、「すべてを満たす求人はご紹介が難しい」と断られました。
体験談7・障がい者手帳未取得で、紹介不可となった
うつ病の診断は受けていたものの、障がい者手帳は未取得。「手帳がない場合は紹介が難しい」と案内され、登録できませんでした。
体験談8・未経験でエンジニア職を希望し、断られた
長年軽作業をしていましたが、在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思ってdodaチャレンジに相談。「未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです」と断られました。
体験談9・通勤が困難で短時間の在宅勤務を希望したが、求人がなかった
身体障がいがあり、フルタイム勤務が難しいため短時間在宅勤務を希望。「現在ご紹介できる求人がありません」と言われました。
体験談10・高い条件(管理職・年収600万以上)を出して断られた
前職では中堅企業で一般職でしたが、障がい者雇用で管理職&年収600万円以上を希望。dodaチャレンジでは「ご紹介可能な求人はありません」との回答でした。

体験談を見てわかるのは、「条件が厳しい」「準備不足」「サポート対象外」など明確な理由があるってこと。自分に合う求人に出会うためのヒントになるね!
dodaチャレンジで断られたときの対処法を徹底解説!

もしdodaチャレンジで断られたら、次にどう動けばいいの?転職できないってこと?
dodaチャレンジで「紹介できる求人がありません」と言われると、ショックを受けてしまうのは当然です。でも、それは「終わり」ではなく「スタート地点の再調整」と考えることが大切です。実際、断られた人の中には、他の選択肢を活かして再スタートを切った方もたくさんいます。
原因を理解し、現実的な対策をとることができれば、転職の可能性はぐっと広がります。スキル不足・職歴の浅さ・ブランクなど、それぞれの状況に合わせた行動が求められます。
ここからは、断られたときにできる具体的な対処法を紹介します。今の自分に必要な準備や選択肢を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてください。

断られた理由を前向きに受け止めて、次の一歩に繋げよう!やり方を変えれば道は開ける!
スキル不足・職歴が浅い場合の対処法とは?
「これまで軽作業や短期バイトしか経験がない」「PCスキルに自信がない」――そんな状態だと、dodaチャレンジでは紹介可能な求人が限られてしまうことも。しかし、スキルアップや新たな経験を積むことで、十分に状況は改善できます。
ここでは、特にスキル不足や職歴の浅さで断られてしまった方に向けて、取り組みやすい対処法を詳しくご紹介します。
- ハローワークの職業訓練を受ける
- 就労移行支援でビジネススキルを習得
- 資格取得でスキルをアピール
ハローワークの職業訓練を利用する|PCスキルの習得が無料・低額で可能
ハローワークでは、失業中や転職希望者を対象にした職業訓練プログラムを用意しています。特にPC操作に不安がある方は、WordやExcel、データ入力などの基本スキルが学べるコースがおすすめ。
受講料は無料またはごく低額で、費用面の負担が少なくスタートしやすいのが魅力です。事務職などへの転職を目指すうえでも、非常に有効な選択肢です。
就労移行支援を活用する|ビジネススキル+メンタル面のサポートも
就労移行支援は、障がいを持つ方のための支援サービスで、実務に近いビジネススキルやコミュニケーションスキル、ビジネスマナーなどが学べます。
また、就職活動のアドバイスやメンタルサポートも受けられるため、自信を持って就活に臨めるようになります。「いきなり就職は不安…」という方にもおすすめのステップです。
資格を取る|MOSや簿記でアピール力アップ!
資格を取得することで、自分のスキルを第三者に証明できるようになります。特におすすめなのは、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級など、実務で使える知識・スキルを証明できる資格です。
こうした資格があると、dodaチャレンジでも紹介できる求人が増える可能性があり、より条件に合った職場に出会えるチャンスが広がります。

スキルや経験が少なくても、今からできることはたくさんある!まずはできるところから一歩ずつ進もう!
ブランクが長くてdodaチャレンジに断られた場合の対処法
「数年以上の離職期間がある」「長期療養で仕事をしていなかった」――そんな場合、dodaチャレンジではサポート対象外となってしまうことがあります。でも諦める必要はありません。
働くことに不安がある方でも、少しずつ段階を踏んで準備していくことで、再び就職のチャンスを掴むことができます。ここでは、長いブランクがあっても無理なく復職を目指せる対処法をご紹介します。
- 就労移行支援に通って生活リズムを整える
- 短時間勤務や在宅ワークから「実績」を作る
- 実習・トライアル雇用でスキルと経験を積む
就労移行支援を利用して就労訓練をする|毎日通所で生活リズムを整える
長いブランクがある方にとって、最初のステップは「生活リズムの安定」です。就労移行支援に通所することで、毎日決まった時間に活動する習慣が身につき、自然と就労に向けた準備が整います。
さらに、企業と連携した職場実習なども体験でき、復職に向けた「慣らし期間」としても有効です。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る|週1〜2回からスタートでもOK
いきなりフルタイムで働くのが難しい方は、短時間のアルバイトや在宅ワークから始めてみましょう。週1〜2日でも継続して働くことで、「働ける状態である」という証拠(実績)になります。
この実績があると、再度dodaチャレンジに申し込むときのアピール材料にもなります。
実習やトライアル雇用に参加する|再登録時の強力な武器に
企業実習やトライアル雇用制度を利用することで、実際の業務に近い形でスキルを磨くことができます。これにより、「即戦力になれるかもしれない」という印象を与えやすくなります。
dodaチャレンジに再登録する際にも、実習経験があることは非常に有利です。ブランクのカバー手段として、ぜひ活用したい選択肢です。

ブランクがあっても大丈夫!段階を踏んで準備すれば、しっかり職場復帰できる可能性は高いよ!
地方在住やフルリモート希望で求人がなかったときの対処法
地方に住んでいると、どうしても障がい者雇用の求人が少ないのが現実です。加えて、完全在宅勤務を希望していると、マッチする求人がさらに絞られてしまうことも。
そんなときでも、視野を広げることで活路が見つかる可能性は十分にあります。ここでは、地方在住や在宅勤務希望の方におすすめの対処法をご紹介します。
- 他の障がい者専門エージェントを活用する
- クラウドソーシングで在宅の実績を作る
- 地域の支援機関に相談する
在宅勤務OKの求人を探す|他の障がい者向けエージェントを併用しよう
dodaチャレンジだけでなく、複数の障がい者専門エージェントを活用するのがポイントです。特に「atGP在宅ワーク」「サーナ」「ミラトレ」などは、在宅勤務に特化した求人が豊富です。
フルリモートにこだわる場合は、これらのエージェントにも登録して、選択肢を広げてみましょう。
クラウドソーシングで実績を作る|スキルなしOKの仕事も多数
「ランサーズ」「クラウドワークス」などのクラウドソーシングサービスを使えば、ライティングやデータ入力などの在宅業務にすぐにチャレンジできます。
実績を積み重ねることで、将来的に正社員在宅求人へ応募するときの実力証明にもなり、非常に有利です。未経験OKの案件も多数あるので、始めやすいのも特徴です。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する
全国展開の転職エージェントでは見つからない、地元密着の求人情報は、地域の支援機関から得られることがあります。
ハローワークや障がい者就労支援センターに相談することで、地元企業の求人に出会えるチャンスが増えます。特に地方では、こうした情報源がとても貴重です。

地方に住んでいても、在宅ワークや地元の支援機関を活用すれば働く道は広がるよ!
希望条件が多すぎて断られた場合の対処法とは?
「完全在宅勤務で週3日、年収◯万円以上」など、条件が多すぎたり厳しかったりすると、dodaチャレンジ側でマッチする求人が見つからず、「紹介できません」と断られることがあります。
でも、それは転職が不可能という意味ではありません。条件の優先順位を見直すことで、紹介可能な求人の幅を広げることができるのです。
- 条件の優先順位を整理する
- 譲歩できる条件を再提示する
- 長期視点でキャリアを考える
条件に優先順位をつける|譲れない条件と希望条件を切り分けよう
すべての希望を満たす求人を探すのではなく、「絶対に譲れない条件」と「できれば希望したい条件」を分けて考えるのが大切です。
たとえば、「完全在宅勤務が必須」と思っていても、「週1〜2回の出社なら許容できる」と少しだけ条件を緩めることで、紹介される求人が大きく増えることがあります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する|再相談で可能性アップ!
一度断られても、条件を見直して再度相談することで、マッチする求人が見つかる可能性があります。
たとえば「週5日勤務は難しいが週4日なら可能」「フルリモート希望だが月1出社はOK」など、柔軟に考えられる点をアドバイザーにしっかり伝えましょう。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる|今できることから始めよう
理想の条件にいきなり合う求人を見つけるのは難しい場合もあります。そこで、まずは条件を緩めてスタートし、キャリアを積んでから徐々に理想に近づく方法もおすすめです。
たとえば「最初は時短勤務から始めてフルタイムに移行」「事務職から経験を積んで専門職へシフト」など、段階的に働き方を整えることで無理なく目標に近づけます。

完璧な条件を求めるよりも、現実的にスタートできる求人から始めると、結果的に理想に近づけることが多いよ!
手帳未取得・障がい区分で断られたときの対処法
dodaチャレンジは障がい者雇用枠専門の転職支援サービスであるため、障がい者手帳を持っていない場合、求人紹介が難しいことがあります。
しかし、手帳がなくても今できることはたくさんあります。手帳の取得に向けて準備したり、手帳が不要な求人にアプローチすることで、転職の道を切り拓くことが可能です。
- 手帳取得の可能性を主治医・自治体に相談する
- ハローワークや就労移行支援で手帳不要の求人を探す
- まずは治療・体調管理を優先し、整ってから再登録
主治医や自治体に手帳申請を相談する|精神・発達障がいでも取得可能な場合あり
精神障がいや発達障がいの場合、「手帳が取れないかも…」と不安に感じる方も多いですが、実は一定の診断条件を満たせば取得できる可能性があります。
まずは主治医に相談し、手帳取得の必要性や見込みを確認しましょう。自治体の障がい福祉課でも手続き方法を詳しく教えてくれます。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK」の求人を探す
手帳がない状態でも、就職活動は可能です。ハローワークには手帳不要の求人もありますし、就労移行支援では体調管理や職業訓練が受けられます。
将来的に手帳を取得してdodaチャレンジに再登録すれば、より条件の良い求人を紹介してもらえる可能性も広がります。
医師と相談して体調管理・治療を優先する|落ち着いてから再登録しよう
無理に就職活動を進めるよりも、まずは体調を整えることが最優先というケースも多くあります。
医師と相談し、治療計画や今後の働き方について見通しを立てることで、タイミングを見て再チャレンジしやすくなります。

手帳がないからって諦めるのは早い!今できることを積み重ねれば、チャンスはちゃんと巡ってくるよ!
その他の対処法|dodaチャレンジ以外のサービスを活用しよう
dodaチャレンジで断られてしまっても、転職の道が閉ざされたわけではありません。他のサービスや支援機関を活用することで、新しい可能性が見えてくることもあります。
他の障がい者向け転職サービスを活用する
以下のようなサービスでは、dodaチャレンジとは異なる視点で求人紹介をしてくれることがあります。
- atGP:障がい者専門の転職エージェント。幅広い求人あり。
- サーナ:学生・既卒者向けの障がい者支援実績が豊富。
- ラルゴ高田馬場:就労移行支援と就活支援の連携型。
地域の支援機関に相談する
ハローワークや障がい者就労支援センターなど、地域密着型の支援機関は、地元の企業とつながりがあるケースが多く、求人情報を得るにはとても有効です。
転職活動は一つの方法にこだわらないことが成功のカギです。複数のルートを併用しながら、自分に合った働き方を一緒に探していきましょう。

「dodaチャレンジだけじゃない」って知っておくと安心!自分に合うサービスを活用して、一歩ずつ前に進もう!
dodaチャレンジで断られた!?精神障害・発達障害でも紹介は可能なのかを解説!

精神障害や発達障害だと、本当に求人を紹介してもらえないの?就職って難しいのかな…
dodaチャレンジに登録してみたけれど、「紹介できる求人がありません」と言われてしまった…。そんな経験がある方の中には、精神障害や発達障害があることが理由では?と不安に感じた方もいるのではないでしょうか。
確かに、障がいの種類や等級、希望条件の内容によっては、紹介が難しくなるケースが存在します。しかし、それは「あなたには働ける場所がない」という意味では決してありません。
たとえば、身体障害のある方は物理的な配慮が必要とされる一方で、精神障害や発達障害の方は環境面や対人関係の配慮が求められるため、マッチングに慎重さが必要となるのです。企業側も、どんな配慮が必要かを具体的に理解している必要があるため、紹介が慎重になるのは当然とも言えます。
重要なのは、障害の特性に合った職場環境や仕事を見つけるための情報提供や準備をしっかり行うことです。正確な情報を整理し、希望する働き方に優先順位をつけることで、紹介される可能性は高まっていきます。

障害の種類が理由で断られたわけじゃない場合もあるんだね。特性に合った求人を探す準備がカギになりそう!
身体障害者手帳を持つ人の就職事情とは?
身体障害者手帳を所持している方は、精神障害や発達障害の方に比べて、企業側の配慮が具体的にしやすいことから、比較的就職しやすい傾向があります。
とはいえ、障がいの部位や程度、職種の特性によっては求人の選択肢が限られてしまうケースもあるため、それぞれの状況に合わせた対策が必要です。
- 等級が軽度なら就職のハードルは低い
- 障がいの内容が「見える化」しやすく配慮しやすい
- 企業側も合理的配慮を設計しやすい
- 身体的制約がある場合は求人に限りが出る
- コミュニケーションに問題がなければ幅広い職種に応募可能
- PCスキルがあれば在宅含めてチャンスが広がる
障害の等級が軽度なら就職がしやすい
身体障害者手帳が6級や5級などの軽度であれば、企業側にとって比較的配慮が少なくて済むケースが多く、オフィスワークや軽作業など幅広い職種での採用につながりやすくなります。
障がいの内容が見えやすい=配慮しやすく採用されやすい
身体障がいは外見や診断書で障がいの内容が明確に分かるため、企業側が「どんな支援が必要か」を判断しやすいのが特徴です。
たとえば車椅子利用ならバリアフリーの導入、片手の不自由さがあればキーボード配置などの工夫が可能。具体的な配慮がしやすい分、企業が採用に前向きになりやすい傾向があります。
企業が合理的配慮を設計しやすい
合理的配慮とは、障がいのある方が働く上で不利にならないように、企業が行う調整や支援のこと。身体障がいはその内容が明確なため、「何をどう配慮すれば良いか」が企業にも伝わりやすく、安心して雇用を進められます。
例:オフィス内のバリアフリー化、作業の一部制限、サポート機器の導入など。
通勤や作業に制限がある場合は求人が限られる
逆に、上肢や下肢に制限がある場合は、通勤や業務内容によって応募できる求人が限られてしまうケースも。
階段しかない職場や立ち作業が多い業種では難しいこともありますが、在宅勤務や事務職など、身体的負担が少ない職種を狙えば十分活躍できる環境が見つかります。
コミュニケーション力があれば、一般職にもチャンスあり
身体障がいがあっても、対人スキルやコミュニケーションに問題がなければ、営業職やカスタマーサポート、一般事務などさまざまな職種での採用が可能です。
「障がいがある=一般職は難しい」というイメージを払拭するには、やはり人とのやりとりがスムーズかどうかがポイントになります。
PC業務や事務職は特に求人が豊富
身体障がい者向けの求人では、PCスキルを活かした業務が特に人気かつ需要があります。たとえば、データ入力、経理、Web更新作業など。
これらは身体的負担が少なく、在宅勤務の導入も進んでいるため、応募できる選択肢が広がりやすい職種です。

身体障がいがあっても、内容が明確だからこそ企業も配慮しやすい!自分の得意を活かしてチャレンジしていこう!
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障がいや発達障がいの場合、企業が特に重視するのは「安定して働き続けられるか」という点です。
過去に長期の休職や頻繁な離職歴があると、企業側は慎重になりやすくなります。定期通院が必要な場合でも安定して働けるか、職場環境の変化にどの程度耐えられるかといった点を意識して、生活リズムを整えてから就職活動を始めることが大切です。
見えにくい障がいだからこそ、企業の不安を払拭する工夫が必要
精神障がいや発達障がいは外見では分かりづらいため、企業側は「配慮が必要なポイントが把握できない」「働き続けられるか不安」と感じることが多くあります。
そのため、応募時や面接時に「自分がどんな職場環境なら安定して働けるか」をきちんと伝えることが重要です。
面接での伝え方が成功のカギ!
面接時には、障がいの特性と必要な配慮を具体的に、かつ簡潔に伝えることが求められます。
例えば「電話対応が苦手なので、業務連絡はメールやチャットにしてほしい」「月1回の通院のため、定期的な休暇が必要」といった形で説明できると、企業側も安心して受け入れを検討しやすくなります。
ただし、過剰な配慮を求めるとマイナス印象になりかねないため、「最低限の配慮で働ける」ことをアピールするのもポイントです。

自分の状態を正しく伝えて、必要な配慮を明確にすれば、企業とのミスマッチを防げるよ!
療育手帳(知的障害者手帳)を持つ方の就職事情
療育手帳を持っている方の場合、手帳の区分(A判定・B判定)によって就職の選択肢が大きく異なります。
どのような働き方が向いているのか、どんな支援が受けられるのかを理解しておくことで、就職活動をスムーズに進めやすくなります。
- A判定(重度)→ 福祉的就労がメイン
- B判定(中軽度)→ 一般就労の可能性が高い
- シンプルな作業、軽作業、補助業務に強い
区分によって選択肢が変わる|A判定とB判定の違いを知ろう
療育手帳にはA判定(重度)とB判定(中軽度)があります。A判定の方は一般就労が難しいケースが多く、就労継続支援B型など福祉的就労が中心になります。
一方でB判定であれば、障がい者雇用枠での一般企業就労も十分に視野に入ります。
A判定(重度)の方は、就労継続支援B型の活用を
重度の知的障害がある方は、まずは無理なく働ける環境として、B型事業所の利用を検討するのが一般的です。
作業訓練や職業リハビリを受けながら、スキルや働く自信をゆっくり育てていけます。
B判定(中軽度)なら、一般企業での就職も可能
中軽度の知的障害の方であれば、清掃や軽作業、補助事務といった職種で、企業の障がい者雇用枠にチャレンジできるチャンスがあります。
また、適切なサポートがあれば通常枠での就労も不可能ではなく、本人の特性と企業の理解度がマッチすれば可能性は大きく広がります。

療育手帳の区分に応じて働き方を選べば、自分に無理のない働き方が見つかるよ!
障がいの種類と就職難易度の違いとは?
障がい者雇用枠の求人においては、障がいの種類によって就職のしやすさに差が出ることがあります。
一般的には、配慮のしやすい障がいほど、企業が採用しやすく、就職のハードルも低くなる傾向があります。
たとえば、身体障害(軽度)は必要な配慮が明確で、企業が対応しやすいため採用されやすい傾向があります。一方で、精神障害や発達障害は外見から障がいが分かりにくく、配慮の方法が企業によって異なるため、採用までに工夫が必要になります。
また、知的障害をお持ちの方の場合、A判定(重度)であれば福祉的就労が中心に、B判定(中軽度)であれば一般就労も視野に入ります。
障がいの特性を理解し、自分に合った支援機関や転職サービスを利用することで、就職のチャンスは確実に広がります。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |

自分の障がい特性を正しく理解して、それに合った支援やサービスを活用することが、転職成功への第一歩だね!
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いとは?自分に合った応募枠を選ぼう
障がいをお持ちの方が就職活動を行う際には、「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」のどちらで応募するかを決める必要があります。
それぞれの雇用枠には特徴があり、自分の体調や職業適性に合わせて選ぶことで、長く安定して働ける職場に出会いやすくなります。
- 障害者雇用枠=法律に基づく配慮付きの枠
- 一般雇用枠=障がいの有無に関係なく競う枠
- 自分に合った枠を選ぶことで、働きやすさが変わる
障害者雇用枠の特徴①|法的義務に基づく雇用制度
障害者雇用枠は、企業が法律(障害者雇用促進法)に基づいて設定している雇用制度です。障がいのある方が安心して働けるような配慮を前提に、採用・勤務が進められます。
障害者雇用枠の特徴②|民間企業は2.5%以上の雇用が義務(2024年4月〜)
2024年4月からは、民間企業における障がい者の法定雇用率が2.5%に引き上げられています。
そのため、一定規模以上の企業は積極的に障害者雇用枠を設け、障がいのある求職者にとってのチャンスが広がっているとも言えます。
障害者雇用枠の特徴③|配慮を前提にした「オープン就労」
障害者雇用枠では、障がいの内容や必要な配慮を企業に開示したうえでの「オープン就労」が基本です。
たとえば、「週1回の通院がある」「静かな職場環境が必要」などを事前に伝えることで、企業も職場環境の調整を行いやすくなります。
一般雇用枠の特徴①|障がいの有無に関係なく競争
一般雇用枠は、障がいの有無を問わず、全応募者が同じ基準で選考を受ける枠です。
そのため、スキルや実績が重視される傾向が強く、配慮や支援は基本的にありません。
一般雇用枠の特徴②|障がい開示は本人の自由(オープン or クローズ)
一般雇用枠では、障がいを開示(オープン)するか、開示しない(クローズ)かを自分で選ぶことができます。
オープンにすると多少の配慮を受けられる可能性もありますが、企業によって対応が異なるため注意が必要です。
一般雇用枠の特徴③|基本的に配慮はないと考えておくべき
一般雇用枠では、定期通院の休暇や業務調整などの特別配慮は原則なしです。そのため、自分の特性に合った環境を見極めることが、より重要になります。

障害者雇用枠と一般枠、それぞれの特徴を理解して、自分に無理のない働き方を選ぼう!
年代別の障害者雇用率とは?年齢によって採用難易度はどう変わる?
障がい者の就職は、年代によって難易度が変わることがあります。一般的には20代・30代の若年層が採用されやすく、年齢が上がるにつれて就職の難易度も上がる傾向にあります。
年齢に応じた対策を行うことが、スムーズな就職活動のカギとなります。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介
厚生労働省が発表した「障害者雇用状況報告(2023年)」によると、障がい者の雇用率は年々増加しており、2023年時点で民間企業の雇用率は約2.3%に達しています。
2024年4月からは法定雇用率が2.5%に引き上げられることもあり、企業の採用意欲はさらに高まると予想されます。
しかし、年代別に見るとやはり差はあり、若年層(20~30代)は未経験OKの求人も多く採用されやすい一方で、40代以上は職務経験やスキルが重視され、難易度が上がる傾向にあります。
とはいえ、年齢が高くてもスキルや経験、PC操作に強みがある方であれば、在宅勤務や専門職の求人で十分に採用される可能性があります。
- 若年層は未経験歓迎の求人が豊富
- 中高年層は経験や専門スキルが求められる
- PCスキルや訓練受講で年齢のハードルを乗り越えられる
| 年代 | 割合(構成比) | 主な就業状況 |
|---|---|---|
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職や転職。未経験OKの求人が多い |
| 30代 | 約25~30% | 経験を活かした安定転職が中心 |
| 40代 | 約20~25% | 職歴によって左右される。未経験職は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 特定スキルや経験を活かした転職が中心 |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務などが中心 |

年齢が上がっても、スキルや工夫次第でチャンスは作れる!年齢に合った求人戦略を立ててみよう!
dodaチャレンジなどの就活エージェントに年齢制限はある?
障がい者向けの転職エージェントを利用しようと思ったときに、「年齢制限ってあるの?」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、dodaチャレンジなどのエージェントに明確な年齢制限はありません。ただし、実際の運用面では50代前半までが中心ターゲットとなっている傾向があります。
年齢制限はないが、実質的には「50代前半まで」が中心
dodaチャレンジをはじめとする障がい者向け転職エージェントは、年齢制限を設けていないものの、紹介される求人の多くが20代〜50代前半向けであることが多いです。
これは、企業側が「長期的に働いてもらえる人材」を求める傾向にあるためで、60代の方への求人紹介は少ないのが現状です。
とはいえ、豊富な経験を活かせる職種や短時間勤務・在宅勤務などの求人も一部にはあるため、希望を捨てる必要はありません。
ハローワークや障がい者職業センターも併用しよう
50代以上の方や、dodaチャレンジで求人紹介が難しいと言われた方は、公的機関の就職支援サービスを併用するのがおすすめです。
- ハローワーク障がい者窓口
- 障がい者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
ハローワークでは、年齢に関係なく応募できる求人を紹介してくれるほか、職業訓練や面接対策・応募書類の添削も行っています。
障がい者職業センターでは、就職に向けたトレーニングや職場実習が受けられ、実務経験のない職種にもチャレンジできるサポート体制があります。
民間エージェントと公的支援を併用することで、年齢に関係なく就職の選択肢が広がります。

dodaチャレンジだけに頼らず、ハローワークや職業センターも活用すれば、年齢問わずチャンスは広がるよ!
dodaチャレンジの口コミはどう?についてよくある質問

dodaチャレンジの口コミって実際どうなんだろう?利用者の評判や断られたときの対応も気になるな…
dodaチャレンジの利用を検討している方の中には、「口コミや評判は信頼できるの?」「紹介されないことってあるの?」と不安を感じている方も少なくありません。
本記事では、dodaチャレンジに関するよくある質問を厳選してご紹介し、それぞれの疑問にわかりやすくお答えしていきます。
さらに、詳細を深掘りした関連ページへのリンクも掲載しているので、気になるテーマがあればぜひチェックしてみてください。

「よくある質問」で不安や疑問をしっかり解消して、納得した上でサービスを使えるようにしよう!
-
Qdodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
-
A
dodaチャレンジの利用者からは、「求人の紹介がスムーズだった」「カウンセリングが丁寧だった」などの良い口コミがある一方で、「希望する求人がなかった」「面談後に連絡が来なかった」といった声も見られます。
実際の口コミや評判を詳しく知りたい方は、以下の関連ページをぜひご覧ください。
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジでは、「紹介できる求人がありません」と言われることもありますが、それは終わりではありません。スキル不足であれば職業訓練を受けたり、他の障がい者向け転職エージェントと併用することで新たな道が開けることもあります。
断られた理由とその対策については、下記の関連ページで詳しく紹介しています。
関連ページ:dodaチャレンジで応募を断られた?その理由や対処法、難しいと感じた体験談とは
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
面談後に連絡が来ない場合、求人とのマッチングに時間がかかっている、企業との調整中、もしくは連絡の行き違いなどが考えられます。
不安な場合は、担当者に一度確認をしてみるのも良いでしょう。具体的な原因と対処法については、以下の関連ページでご紹介しています。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡がない…その理由と対処法|面談・求人・内定のケースごとに解説
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、これまでの職務経験や希望条件、障がいの特性、配慮が必要なポイントなどについて丁寧にヒアリングされます。
事前に自分の強みや働き方の希望を整理しておくと、スムーズにやり取りが進みます。
面談の流れや聞かれる内容についての詳細は、以下の関連ページをご覧ください。
関連ページ:dodaチャレンジ:面談から内定へ!流れを知り、注意点・対策を万全に準備しよう
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいのある方に特化した転職支援サービスです。
登録するとキャリアアドバイザーがつき、希望に合った求人紹介だけでなく、応募書類の添削、面接日程の調整、選考対策など総合的なサポートを受けることができます。
障がい者雇用枠の転職活動をスムーズに進めたい方におすすめのサービスです。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジで紹介される求人は、主に障がい者雇用枠となるため、障がい者手帳を所持していない場合は求人紹介が難しいケースがあります。
ただし、今後手帳の取得を考えている方は、キャリアアドバイザーに相談することで手続きのアドバイスが受けられる場合もあります。
関連ページ:dodaチャレンジの利用には手帳が必要?手帳なし・申請中でも使えるのかを解説!
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類に関係なく基本的に登録可能ですが、支援の対象外と判断されるケースもあります。
特に、長期間のブランクがある方や体調が安定していない方は、まずは就労移行支援の利用を勧められることもあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
退会を希望する場合は、担当のキャリアアドバイザーへ直接連絡するか、公式サイトのお問い合わせフォームから手続きが可能です。
事前に転職活動への影響や再登録の可否などを確認しておくことをおすすめします。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、基本的にオンライン(電話またはWeb面談)で実施されます。
対面での相談を希望する場合は、対応可能な地域があるため、事前に確認しておくと安心です。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには明確な年齢制限はありませんが、実際には50代前半までが対象となる求人が多いです。
50代後半以降の方は、ハローワークの障がい者窓口や職業センターなど公的支援機関の併用が効果的です。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中でもdodaチャレンジのサービスを利用し、転職活動を進めることが可能です。
ただし、直近の職歴がない場合やブランクが長い場合は、紹介される求人が限定される場合もあります。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは転職エージェントのため、新卒向けの求人はほとんど取り扱いがなく、学生の利用は難しいケースが多いです。
就活中の学生は、大学のキャリアセンターや新卒向け障がい者就職支援サービスを利用するのがおすすめです。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較

dodaチャレンジって本当に求人を紹介してもらえるの?他のサービスと何が違うのか気になるな…
dodaチャレンジを利用する際、「本当に自分に合った求人を紹介してもらえるのか?」「他の障がい者向け転職サービスとどう違うのか?」といった疑問を感じる方も多いでしょう。
実際のところ、dodaチャレンジでも状況次第で求人紹介を断られるケースは存在します。
ただし、それはdodaチャレンジに限らず、他の障がい者向け就職エージェントでも同様で、どのサービスでもマッチングの可否は求職者のスキル・希望条件・体調などに大きく左右されます。
この記事では、dodaチャレンジの特徴を他の就職支援サービスと比較しながら、「どんな人に合っているのか」「断られたときはどうすべきか」などを解説していきます。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
|---|---|---|---|
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー (atGP) |
1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビ パートナーズ紹介 |
350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援 ミラトレ |
非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッド チャレンジ |
260 | 東京、神奈川、 千葉、埼玉、大阪 |
全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、 東海、福岡 |
全ての障害 |

dodaチャレンジと他サービスをしっかり比較することで、自分に合った就職サポートが見つけやすくなるよ!
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ

dodaチャレンジで断られたとき、どう対処すればいいのか不安になるけど、他の選択肢もあるのかな?
dodaチャレンジは、障がいのある方に向けた転職支援サービスとして多くの実績がありますが、登録したすべての人に求人が紹介されるわけではありません。「紹介できる求人がない」「条件に合わない」といった理由で断られることもあるため、事前にその仕組みや傾向を理解しておくことが重要です。実際には、スキル不足や希望条件の厳しさ、就労経験の有無、体調の安定度、障がい者手帳の有無などが影響しており、これらをクリアできれば再度チャンスを得ることは可能です。
また、dodaチャレンジで断られたとしても、他の障がい者向け転職サービス(例:atGP、サーナ、ミラトレなど)や、ハローワーク・障がい者職業センターといった公的機関を活用することで選択肢は広がります。さらに、クラウドソーシングや就労移行支援などを通じて実績を積むことも、将来的な就職に有利に働きます。
大切なのは、一度の不採用や断りに落ち込まず、自分に合った働き方や支援方法を見つけることです。今回紹介した体験談や対処法を参考に、自分の状況に合った転職戦略を見直してみてください。

dodaチャレンジでうまくいかなかったとしても、あきらめずに次の一歩を踏み出せば、きっと自分に合った働き方が見つかるはずです!