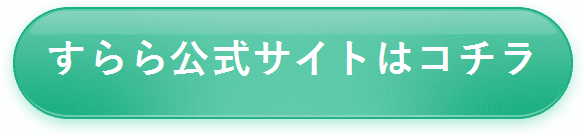すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
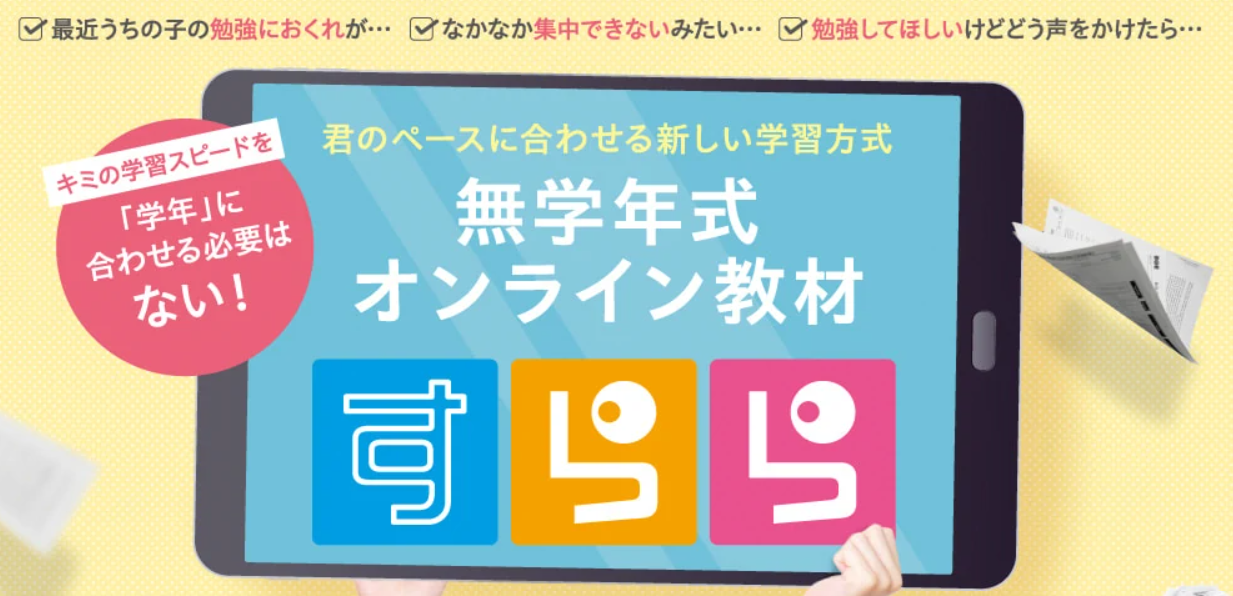

なぜすららは出席扱いとして認められやすいの?その仕組みを知りたい!
すららは、不登校の子どもたちでも学校の「出席扱い」として認定される可能性があるオンライン学習教材です。文部科学省が示す「ICTを活用した学習の出席扱い制度」に対応しており、条件を満たせば自宅学習でも出席として認められるようになります。
その大きな理由のひとつが、学習の質と記録の証明力です。すららでは、子どもがどの教材をどれだけ学習したか、どの程度理解しているかといったデータがシステム上で自動的に記録されます。保護者が手動で記録する必要はなく、データをレポートとして提出することで、学校も客観的に学習状況を把握しやすくなります。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは「ただの教材」ではなく、学習の履歴や進度を記録するシステムが搭載されています。学習内容と成果が「見える化」されていることで、学校側も安心して出席扱いとして判断できます。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららのシステムでは、毎日の学習履歴や正答率、理解度などのデータを自動的に蓄積。それをもとに作成される「学習進捗レポート」は、学校に提出可能で、出席扱いの判断材料になります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される
保護者が管理表を作成する必要がなく、すらら側で進捗状況が可視化されるため、学校にも安心材料として受け入れられやすいという利点があります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららでは「無学年式」を導入しており、自分のペースで進められる学習設計が特徴です。さらに、すらら専属の「すららコーチ」が個別に学習プランを作成してくれ、進捗も一緒に見守ってくれます。
すららはコーチがいることで、「計画性」と「継続性」を両立できる
子どもの理解度に応じてコーチが適切な学習計画を提案し、定期的に見直しながら継続できるようサポート。これにより、計画的かつ持続的な学習が可能になります。
専任コーチが学習進捗をフォロー
進捗のズレや学習の停滞にも素早く対応できるよう、コーチが保護者とも連携してフォローアップしてくれるので安心です。
無学年式で自由な学び方ができる
得意な単元はどんどん先へ進み、苦手な単元には戻って学び直せる。こうした柔軟なシステムが、学習の遅れを感じさせず、自己肯定感の向上にもつながります。

すららは記録・サポート・学習設計すべてが整っているから、出席扱いになりやすいのも納得だね!
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

すららって、学校との連携までサポートしてくれるの?どんなふうに関わってくれるのか知りたい!
すららでは、不登校のお子さんが出席扱いとして認められるための学校との連携支援も手厚く行われています。家庭と学校がスムーズに連携を取れるように、必要なサポート体制が整っているのが特長です。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いを申請する際に必要となる書類について、すららが案内してくれるので、初めての保護者でも安心して申請を進めることができます。
学習レポートの提出もフォローしてくれる
すららでは、出席扱いに必要な「学習記録レポート」のフォーマットも用意されており、専任コーチが提出のフォローまでしてくれます。学校側への説明もスムーズに行えます。
学校との連絡もサポート
担任や校長とのやり取りに不安がある場合でも、すららが連携支援を行い、必要に応じたサポートをしてくれるため、家庭だけで抱え込まずに済む体制が整っています。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
全国の教育委員会や学校で導入されている実績ある教材であるため、学校側の信頼も高く、不登校支援として導入されるケースが増えています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
文部科学省が定めるガイドラインに対応しており、「不登校支援教材」として多くの学校で採用されています。出席扱いとして認められやすい背景には、この公的な信頼も影響しています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
文部科学省の学習指導要領に準拠した内容でカリキュラムが構成されており、学校の授業と同等の内容を自宅で学ぶことができます。
学習の評価・フィードバック体制がある
すららは学習の進捗をもとに評価が行えるシステムを導入。テスト機能や解答履歴、正答率の記録などがあるため、学校側も客観的に学習の質を評価することができます。

実績と制度の整備があるから、すららなら安心して出席扱いの申請ができそうだね!
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

出席扱いの申請ってどうやって進めるの?具体的な流れや必要なものが知りたい!
すららを利用すれば、不登校の子どもでも条件を満たせば出席扱いになる可能性があります。ただし、そのためには学校や教育委員会との連携と、きちんとした申請手順を踏むことが大切です。以下に、申請の流れとポイントを詳しく解説していきます。
申請方法1・担任・学校に相談する
まずは学校の担任や校長に相談し、出席扱いの対象になるかを確認することが最初のステップです。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
多くの場合、学習記録や申請書が必要になります。場合によっては医師の診断書が求められることもあるため、詳細を学校側に確認しましょう。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
医師の意見が必要なケースでは、準備を怠らないことが大切です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
精神的な理由や健康上の理由などで登校が難しい場合、診断書があることで学校側の理解を得やすくなります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
医師に相談する際は、「家庭で学習を継続していること」や「出席扱いを希望していること」をしっかり伝えましょう。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららでの学習データは、出席扱いを申請するうえで重要な証拠になります。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのレポート機能を活用して、客観的な学習の記録を提出することで、申請がスムーズに進みやすくなります。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
申請書は学校側が用意しますが、家庭での学習状況を補足資料として用意しておくと安心です。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
最終的には、学校長や教育委員会の承認が必要になる場合もあります。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
必要な書類を提出し、学校長の判断で出席扱いが認められます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては教育委員会の承認も必要です。学校との連携を密にして進めましょう。

申請の流れがわかれば、すららで出席扱いを目指す準備もしやすくなりますね。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

出席扱いになったら、どんな良いことがあるの?進学や気持ちの面でも違いがあるのかな?
すららを通じて出席扱いを認めてもらうことには、多くのメリットがあります。特に不登校の子どもにとっては、学習面や精神面での不安が大きいため、制度をうまく活用することで安心して学びを継続できる環境を整えることができます。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席日数が評価に直結する内申点は、進学にも大きく影響します。出席扱いが認められることで、欠席としてカウントされず、成績への悪影響を避けることが可能になります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
出席扱いが適用されれば、欠席が続いても評価を大きく落とさずに済み、進路の選択肢が保たれやすくなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点が進学に影響するため、出席扱いは大きなアドバンテージとなります。継続的な学習と証明によって将来の可能性を広げることができます。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校で授業が受けられないことで「遅れているかも…」という不安を抱くこともありますが、すららならその心配を軽減できます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
無学年式のシステムを採用しているすららでは、学年に関係なく理解度に応じた学習が可能です。遅れた単元に戻ることも、先取りすることもでき、柔軟な学びが可能です。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
継続的な学びによって「できる!」という実感が得られ、自信を持てるようになります。精神面でも前向きになり、不登校による不安もやわらぎます。

出席扱いが認められることで、勉強の継続や進学のチャンスが広がり、親子の安心にもつながるんですね。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを支える中で、保護者も大きなストレスを抱えることがあります。特に「学習の遅れ」や「進路の不安」など、先の見えない状況に心を痛める親御さんは少なくありません。ですが、すららを活用して出席扱いが認められることで、その不安は大きく軽減されます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららには、学習支援を専門に行う「すららコーチ」が在籍しており、保護者だけが子どもを支えるのではなく、学校や家庭と三者で連携しながら学習を見守る体制が整います。コーチが伴走してくれる安心感は、保護者の心理的負担を大きく減らしてくれます。
メリット4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の多くの自治体・学校で導入されており、その信頼性は非常に高いです。不登校支援として活用されている実績があるからこそ、学校側も安心して導入・出席扱いの判断をしやすくなっています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
文部科学省が後押しする「不登校支援教材」として、すららはすでに多くの場面で認められています。制度に沿った活用ができる教材として、学校も安心して対応しやすく、保護者にとっても安心材料となるでしょう。
メリット5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
文部科学省の学習指導要領に準拠したカリキュラムが提供されているため、家庭での学習でも学校と同様の内容をしっかり学ぶことが可能です。授業に遅れることなく、安心して学習を進めることができます。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
進捗状況の記録、テストによる理解度チェック、定期的なフィードバックが自動で行えるため、学校に準じた学習環境が整っていることを示す材料になります。このような仕組みにより、学校側も出席扱いを判断しやすくなっています。

「出席扱い」が認められることは、子どもだけでなく、保護者や学校にも大きなメリットがあるんですね。支援体制が整っているすららなら安心して取り組めそうです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

「すららで本当に出席扱いになるの?」という疑問、申請のときに注意すべきポイントって何?
すららを使って不登校の子どもが出席扱いになるためには、いくつかの大切な注意点を押さえておく必要があります。申請手順や書類の準備が万全であっても、学校や教育委員会との連携が取れていなければ、うまくいかないケースもあるのです。ここでは、申請時の重要な注意点をしっかり解説していきます。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを申請するには、何よりもまず学校側の理解と協力が必要不可欠です。すららが文部科学省の指針に準拠した教材であることをしっかりと伝えることで、安心感を持ってもらうことが大切です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
中には、ICT学習による出席扱い制度について詳しく知らない学校関係者もいます。そうした場合には、すららが文科省ガイドラインに基づいて開発された学習教材であることを丁寧に説明しましょう。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生とも連携することが成功のカギです。すららの公式資料を印刷して持参すれば、話の流れもスムーズに運びやすくなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書が求められることもあります。これは、出席扱いを正式に認めてもらううえで、学習を継続できる状態であるという第三者の証明が求められるためです。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
特に精神的な不調が理由となる場合、心療内科や小児科からの診断書があることで、学校側も柔軟に対応しやすくなります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を依頼する際には、「学校に提出するための診断書」であることを明確に伝えると、より適切な書式で対応してもらいやすくなります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書の内容には、家庭での学習状況や意欲的な学習の取り組みが盛り込まれているとベストです。すららで日々どのように学習を進めているかを、医師に詳しく共有しておきましょう。

学校との関係性と、医師の診断内容が申請の成否に大きく関わってくるんですね。すららの取り組みをきちんと伝えることが大切です。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いを目指すなら、家庭学習の内容が学校の授業と同等であることが重要です。ただ自習するだけでは不十分で、文科省の学習指導要領に準拠した内容であることが求められます。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
すららは、教科書準拠のカリキュラムに沿って学べる教材のため、好きな教科だけを選ぶのではなく、計画的に全体を学習することが大切です。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
1日2〜3時間を目安に継続的に学ぶことが、出席扱いの審査で好印象につながります。継続的な学習姿勢が認められるためには、一定時間を確保しましょう。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
国語や数学だけでなく、理科・社会・英語なども含めて、全教科をバランスよく学ぶことが大切です。学校のカリキュラムに準じた学びが前提になります。

出席扱いにするためには、勉強時間も内容も「学校並み」が求められるんですね。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
すららを利用するだけではなく、家庭での学習状況を学校にしっかり報告することが求められます。学校との連携がスムーズであるほど、出席扱いの認定もスムーズになります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららの学習レポートを活用し、進捗や取り組み内容を月に1回程度、担任や学校に提出しましょう。これにより、継続的な学習姿勢を学校に示すことができます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学習の様子を確認する目的で、家庭訪問や面談を求められる場合もあります。積極的に対応し、子どもがどのように学習しているかを共有することが大切です。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
メールや電話で、こまめに進捗を伝えることも重要です。小さな報告でも積み重ねることで、学校側の安心感につながります。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
自治体によっては、教育委員会の承認が必要となる場合があります。その際は学校と協力しながら、申請資料の作成を進めていくと良いでしょう。

「学校と連携しながら継続的に学習を進めること」が出席扱いの最大の鍵ですね。すららの仕組みをうまく活かしましょう!
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

どうすれば「すらら」を使って出席扱いにしてもらえるの?具体的な成功のコツが知りたい!
「すらら」は、不登校の子どもでも学校での出席扱いを認めてもらえる可能性があるオンライン教材ですが、申請がスムーズに通るかどうかは事前の準備次第。ここでは出席扱い成功のポイントを4つ紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いを認める判断材料として、他校での前例が大きな後押しになります。「すららで出席扱いになったケース」を紹介し、信頼性を伝えましょう。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
すららは多数の導入実績があり、公式サイトにも紹介されています。これを活用して学校側に具体的なデータを示すことで、安心感を持ってもらえます。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
出席扱い成功の事例を印刷して持参することで、教員に「うちの学校でもできるかも」と思ってもらいやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いの判断には、本人の学習意欲も重要です。やる気があることを学校に伝えることで、認定されやすくなります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
簡単なメモや作文で構いません。「毎日どんなふうに頑張っているのか」や「将来の目標」などを記録し、担任や校長に見せると大きな効果があります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
本人の口から直接意欲を伝えると、先生の印象も大きく変わります。対面のやり取りができれば、成功率もアップします。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
短期間だけ頑張っても意味がありません。無理なく続けられる学習スケジュールがあることを示すことが大切です。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
背伸びしたプランよりも、確実に続けられる学習ペースを提案しましょう。無理のないスケジュールが信頼を生みます。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららの専任コーチと相談しながら学習計画を作成すれば、説得力のある学習プランとして学校にも伝えられます。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららには、学習サポートを行う「すららコーチ」がついています。申請書や学習証明の作成も支援してくれるため、ぜひ活用しましょう。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
進捗レポートの出力やフォーマットの準備も、すららコーチがしっかりフォローしてくれます。書類作成の不安があっても大丈夫です。

「学校への説明資料」「学習意欲の見せ方」「無理のない計画づくり」が成功のポイントですね。すららの機能を最大限に活かしましょう!
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

すららを使っている家庭って、実際どう感じているの?リアルな口コミが知りたい!
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

良い点もあれば改善してほしい点も。リアルな口コミから、自分に合うかどうかをしっかり見極めましょう。
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららを使えば不登校でも出席扱いになるって本当?どういう条件なのか気になる!
すららは、不登校の子供の学習支援として活用できる教材ですが、出席扱いになる条件や申請方法について疑問を持つ方も多いかもしれません。学校への説明の仕方や必要書類など、具体的に何を準備すればよいのか分からないという声もよく聞かれます。また、受講費や学習サポート体制といった料金面の疑問、発達障害のあるお子さんでも使えるのかといった点も気になりますよね。ここでは、すららを利用する上でよくある質問をまとめて紹介していきます。

実際に利用を検討している人が抱えやすい疑問を、先に知っておくと安心です。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに関する口コミの中には、「うざい」と感じる声が一部存在します。これは、アニメーションを使ったキャラクターによるナビゲーションや音声のやり取りが、子どもによっては過剰に感じられたり、飽きやすかったりすることが原因の一つです。特に、学習に対して自主性が高い子どもには「自分のペースで進めたいのにキャラが干渉してくる」と感じることもあるようです。一方で、声かけがあることで学習を続けやすいと感じる子もいるため、使い心地はお子さんとの相性によって異なります。実際の口コミや体験談を参考に、自分に合ったスタイルかどうかを検討することが重要です。
関連ページ:すららは本当にうざい?最悪との口コミの真相や料金、小中高向けタブレット教材の評価を紹介!
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには、発達障害に特化した「専用コース」はありませんが、すららの通常コースの中で発達障害のあるお子さんにも対応できるよう配慮されています。たとえば、無学年式でつまずいたところに戻って学べる仕組みや、すららコーチによる個別サポートがあることで、発達に特性のある子供でも安心して取り組めるよう設計されています。料金は基本的に通常の学習コースと同じで、選択する教科数(1教科・3教科・5教科)や支払い方法(月払い・年払い)によって異なります。詳細はすらら公式サイトで確認することをおすすめします。
関連ページ:すららの料金は発達障害や学習障害の方に割引がある?療育手帳で安くなるのかをチェック!
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららは、不登校の子どもが自宅で継続的に学習できる教材として、一定の条件を満たせば「出席扱い」として認められることがあります。これは文部科学省が推進する「ICTを活用した学習の出席扱い制度」に基づいており、学校と教育委員会の判断によって適用されます。重要なのは、すららでの学習が学校の授業に準ずる内容・時間であること、そして学習記録をレポートとして学校に提出することです。申請には学校との事前相談や必要書類の準備が求められるため、詳細な流れは関連ページで確認し、早めに学校と連携することが大切です。
関連ページ:すららを活用して不登校でも出席扱いに!申請手順や注意点、成功の秘訣を解説
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、期間限定のキャンペーンコードが配布されることがあります。これを利用することで、入会金の割引や無料体験などの特典が受けられることがあります。キャンペーンコードの入手方法は、すららの公式サイトやメルマガ、SNS、提携サイトなどで告知されることが多く、タイミングによって内容も異なります。コードを取得したら、入会手続きの際に指定の入力欄に入力することで特典が適用されます。事前の確認と入力忘れに注意しながら、お得に申し込みましょう。
関連ページ:すららのキャンペーンコードをゲット!入手方法や無料特典の詳細をチェック
すららの退会方法について教えてください
すららを退会したい場合は、公式サイトの「マイページ」から手続きが可能です。退会手続きは自動的には停止されないため、解約の意志がある場合は忘れずに手続きを行う必要があります。また、手続きのタイミングによっては翌月分の料金が発生することがあるため、更新日前に余裕を持って確認しておくのがおすすめです。公式サイトの「よくある質問」ページには、解約の手順が詳しく掲載されているので、参考にしながら正しく進めてください。
関連ページ:すららの退会・解約・休会の方法とは?手続きの流れや期限を解説!
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららの基本的な料金体系は、入会金と月額受講料のみというシンプルな設計になっています。そのため、教材の購入費などの追加費用は基本的に発生しません。ただし、学習を進める上で必要なパソコンやタブレット、インターネット環境などは自分で準備する必要があります。また、希望する場合には有料で追加サポートサービスを受けられるオプションもありますので、必要に応じて公式サイトをチェックしておくと安心です。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは1アカウント=1名が基本の利用ルールです。そのため、兄弟や姉妹で学習したい場合は、それぞれが別々のアカウント契約をする必要があります。学習履歴や進捗が個別に管理されるため、正確な出席扱いの記録や学習サポートの提供を維持するためにも、共有ではなく個別の契約が推奨されています。とはいえ、兄弟での複数利用に関する特典や割引が用意される場合もあるため、気になる方は公式サポートに直接問い合わせてみましょう。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生向けコースには英語を含んだ5教科コースがあります。標準では国語・算数・理科・社会の4教科ですが、英語をプラスしたコースを選択することで、小学生のうちから無理なく英語学習をスタートすることが可能です。すららの英語はアニメーションや音声付きの反復学習が特徴で、初学者でも楽しく学べる工夫がされています。英語コースの詳細や学習内容は公式サイトで確認できます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの大きな魅力の一つが「すららコーチ」の存在です。コーチは子どもの学習状況を定期的に把握しながら、学習計画の作成や進め方のアドバイス、学習習慣の定着サポートなどを行います。特に不登校や発達障害のあるお子さんには、個別対応での指導や声かけを行ってくれるので、無理なく学習を継続しやすい環境が整っています。保護者とのやり取りも丁寧で、学習状況に応じたレポート作成のサポートもあるため、学校との連携もしやすくなっています。
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

他の教材と比べて、すららはどんな点が「出席扱い」に有利なんだろう?
不登校の子どもにとって、自宅での学習手段としてタブレット教材の選択は重要です。特に「出席扱い」として認められるかどうかは、将来の内申点や進学に大きく影響します。すららは、文部科学省のガイドラインに沿った学習教材として公式に認められており、実際に多くの自治体や学校で出席扱いの前例があることが強みです。
一方で、他の家庭用タブレット教材も人気がありますが、「出席扱い」の観点から見たときのサポート体制や学習記録の提出のしやすさでは、すららの方が優位なケースが多いです。特に、すららコーチによる学習支援や、レポート提出のフォロー体制が整っている点は、保護者にとって大きな安心材料となります。
さらに、無学年式で学習ができるという特徴は、学年にとらわれずに「戻り学習」や「先取り学習」ができるため、個別のペースに合わせて無理なく進められるのもメリットです。出席扱いの制度を利用したい家庭にとって、どの教材が適しているかを比較する上で、すららの導入実績やサポート体制は大きな判断材料になるでしょう。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
|---|---|---|---|---|
| スタディサプリ 小学講座 |
2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数 理科、社会 |
✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ 小学生コース |
3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
✖ |
| オンライン 家庭教師東大先生 |
24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数 理科、社会 音楽、図画工作 |
必須 |
| デキタス 小学生コース |
3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数 理科、社会 |
✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い 英単語・計算 |
必須 |
| LOGIQ LABO (ロジックラボ) |
3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師の サクシード |
12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数 理科、社会 |
✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは実績やサポート体制の面でも、出席扱いを目指す家庭には特におすすめの教材と言えそうだね。
すららを活用して不登校でも出席扱いに!申請手順や注意点、成功の秘訣を解説まとめ

最終的に、すららは不登校の子どもにとって本当に出席扱いとして有効なの?
すららは、不登校の子どもが安心して自宅で学習を進めることができるオンライン学習教材です。文部科学省が定める「ICTを活用した出席扱い制度」にも対応しており、学習記録の提出・継続的な学習支援・学校との連携といった要件を満たすことで、実際に多くの学校で出席扱いとして認められた実績があります。
ただし、すべてのケースで必ず認められるわけではなく、学校や教育委員会の判断が必要となります。そのため、申請前には必ず学校に相談し、必要書類や条件を確認した上で、「すららコーチ」のサポートを活用して学習記録や計画をしっかり整えることが成功のカギです。すららでは、フォーマットの提供や書類提出のフォローも行っており、保護者の負担を軽減しながら進められる点も大きなメリットです。
学習の遅れを取り戻すだけでなく、公式サイトで紹介されている通り、自己肯定感の向上や家庭の雰囲気の改善にもつながったという声も多く見られます。よくある質問ページも活用しながら、制度を正しく理解し、安心して出席扱いの申請を進めてみてください。

制度を正しく理解し、学校との連携を深めながら進めれば、すららは出席扱いの実現にとても有効な教材だね!